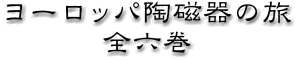
乾いた大地、照りつける太陽、逝る血と惰熱。
ムーア人が求めた地上の楽園はヨーロッパ近世陶磁器発祥の地となり、
その彩色陶器はマヨリカ陶器としてイタリアヘ伝えられた。
アズレージョと呼ば札る白地に藍の装飾タイルに彩られる
ポルトガルの街角。
人の温もり、激しさと同時に涼しさを伝える陶器は、ただの土の塊ではあり得ない。
美しい職人の手技にチンチン(乾杯)!
第二巻 イギリス編 第三巻 ドイツ編 第四巻 南欧編 第五巻 北欧編 第六巻 トルコ編 ※ 定価
920円 (税込み)

第一巻
フランス編
ロココの華が生んだ青
女王陛下の愛した器
東洋の白に憧れて
半島の光と影
白夜に咲く藍の花
文明の交差点に眩惑を感じて
第四巻 南欧編
CONTENTS
泥のように酔い、巡礼者のように清貧だった陶工たち――はじめに 7
イタリア 11
静誼な聖地の産んだ色鮮やかな陶器――ペルージアからアッシジヘ 12
陶器発展の中心地――ファエンツァ 21
歳月に色槌せぬ都市――フィレンツエ 30
バルジェロ国立美術館 37
イタリアの白い太陽――リチャード・ジノヅ窯 42
オーナーの好みに調えられたホテル――ホテル・リージェンシー 56
ヴィラ・ジュリア博物館 60
ローマ大学 ジュリアーノ・マナコルダ教授 66
タイルのあるホテル巡り 1――ホテル・サンピエトロ・ディ・ポジターノ 72
タイルのあるホテル巡り 2――ホテル・カラ・ディ・ヴォルペ 76
スペイン 81
イスラムの絢燭を残した都市――セビーリャ 82
十世紀に最盛期を迎えたイスラムの王都――コルドバ 93
荒々しい海岸の窯――ラ・ビズバール 101
遊び心に満ちた芸術家たち――バルセロナ 109
夢を閉じこめた器――リアドロ 118
イスラムから持ち込まれたエナメル釉――ヒメノ窯 124
翼を持つ壼――マドリード 133
国営城館の宿パラドールを訪ねて1――グラナダ 141
国営城館の宿パラドールを訪ねて2――アルバセーテ 146
ポルトガル 153
アズレージョから始まったポルトガルの旅――ポルト 154
染付けタイルに飾られた街――アヴエイロ 158
ポルトガルで焼かれるイマリ――ヴィスタ・アレグレ窯 163
ローマ都市の遺跡に建つ窯――コニンブリガ窯 173
自然賞賛の伝わる器――ボルダロ・ピニュイロ窯 179
アズレージョを博物館に訪ねて――リスボン 185

ラ・マンチャの国道を疾走した。

マドリッドの装飾美樹幹に保存された18世紀の台所。
|
 看板もさすがに陶器で造られていた。
場所がかわってイベリア半島である。コルドバに向かう途中、耳が片方だけ垂れた犬を伴った羊飼いの老人に出会った。飄々と訥々と、それでいて炯々とした眼力で老人はいった。
 顔料容れのパレット?にも意地があるようだ。 |
|
ヒメノ窯
バレンシアから車で約二〇分、灼熱の太陽を浴びて育った陶芸の街、マニセスに着いた。 車内はすでにサウナ風呂のように暑いが、街角の壁に埋め込まれたタイル絵が、涼しい風を送ってくれているようだ。眩しい表情の陶器が売られていた。緑や青で絵付されたエナメル釉で、どれもがイスラム風の装飾である。朽ちた門扉の前で店番をしていた老人は、とても愛想がよく、カメラを向けても微笑を絶やすことがない。おまけにオレンジを三つもプレゼントされた。その場で皮をむき、一気に食べたがさすがオレンジ大国、その味はこの地を支配していたアラビア人をも魅了したであろう、美味そのものであった。
 街道沿いに生活雑器を売る店が軒を競っていた。
 天井も焼き物であったヒメノ窯の付属美術館。 ヒメノ家は代々陶器造りを家業としており、彼の父ホセ・ヒメノさんで三代目であった。 現在のヒメノ窯の繁栄は、もちろんビセンテさんの努力にもよるが、「やはり父が偉大であったからでしょう」と彼は一枚の写真を見せてくれた。写真には一九六六年と記されていたが、これは人間国宝のような称号をフランコから与えられ、その授与式の様子が写っていた。ホセ・ヒメノは一九六七年に他界したが、当代のビセンテさんが跡を受け継いだわけである。  日本に持ち帰りたかった陶製の鳥籠。 「一六世紀ころには、イタリアが多彩色の陶器をつくりはじめたからマニセスの輸出量が減ってね。イタリア人は我々から学んだ技術をもって、逆にこちらに売り込んできたね」 案内しながらビセンテさんは、さらにマニセスの歴史を教えてくれた。 |
![]() 参考図書
参考図書![]()
脇田宗孝『世界やきもの紀行その源流を訪ねて』(美術書出版 )
三上次男 . 『ペルシアの陶器 』(文藝春秋)
『ヨーロッパの陶磁』(岩崎美術社)
『ヨーロッパ陶磁名品図鑑』(講談社)
『ヨーロッパ名窯図鑑』(講談社)
前田正明『西洋陶磁物語』(講談社)
『陶藝の美』(京都書院)由水常雄
『図説西洋陶磁史』(ブレーン出版)
三上次男 『陶磁の道』(岩波書店)
西田宏子『一七・一八世紀の輸出陶磁』(毎日新聞社)
冨岡大二『吉陶磁の見方のコツ』淡交社
『伊万里』(学研)
三杉隆敏『やきもの文化史』(岩波文庫)
〜
スペインに関する問い合わせ〜
東京部港区虎ノ門3−1−10 第2虎ノ門電気ビル4F
TEL 03−3432−6141
![]()
